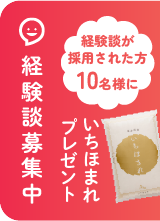戦前から現代まで、
社会が変われば
恋愛観も変わる
おおまかには、伝統的・封建的な家制度に基づいた結婚観が主流であったものが、時代とともに徐々に、自由恋愛という考え方が強まっていったといえます。
日本の場合、戦前、例えば大正デモクラシーの時代などに、自由恋愛を主張する文学・文化等がもてはやされたことがありました。ですが実際にその風潮が家制度を壊すまでには至りませんでしたが、少しずつ「自由に恋愛がしたい」という考え方が一部の人の間で支持されていきました。
第二次世界大戦後は、アメリカ文化の影響により思想としての自由恋愛はさらに少しずつ広まっていきます。それに伴い、結婚のきっかけもいわゆる見合い結婚から恋愛結婚へと変化していきます。戦前には見合い結婚が約7割を占めていましたが、その比率は徐々に減少し、1960年代末には恋愛結婚の方が上回るようになります。1970年前後には女性の解放をうたったウーマンリブ運動も強くなっていきました。そして高度経済成長期からバブル期(1970~1980年代)の時期に、経済的な豊かさの確立もあいまって、テレビドラマやクリスマス等のイベントなどに代表される華やかな自由恋愛の文化が一世を風靡しました。この高度経済成長期からバブル期にかけて、今の親世代である40~50代の人が生まれ育ってきたわけです。バブル期の華やかさこそなくなりましたが、恋愛形態の多様化という形で、自由恋愛が現在につながっていると考えられます。
恋愛や結婚の多様化にはいろいろなものが含まれます。以前は、自由恋愛の終着点として結婚をして家庭を築くという考え方が主流でしたが、結婚を前提としない恋愛や、結婚をしても子どもを作らない家庭など、いろいろな終着点をめざす人がいます。これまでは恋愛は異性との間で行われるのが通常で、同性との恋愛は異常なものと捉える傾向がありましたが、現在ではLGBTQ+という様々な性の捉え方が広く認められ、男性同士、女性同士の恋愛も一つの恋愛形態であり、それを公言することも多くなっています。そもそも恋愛をしないという選択をする方もいます。さまざまなアプリやSNSなどの発展が、こうしたいろいろな価値観を表現し、同じ価値観の者同士が結びつく機会を提供しているといえるかもしれません。
親は戦後の高度経済成長を知る世代に育てられ
子は社会構造が大きく変わる時代に育てられた
戦後、女性の参政権が認められて男女平等の考え方が普及していく一方で、高度経済成長を支える家族形態として「働く父親と家庭を守る母親」という家族モデルが中心的なイメージになっていました。女性は結婚とともに退職するという職場の雰囲気もありました。学校教育に目を向けますと、小学校・中学校では一定の男女平等の教育を受けつつも、高校や大学では、男子のみ・女子のみという教育形態が一つの大きな役割を担っていました。
1985年に制定された「男女雇用機会均等法」をきっかけに1990年代頃より働き方などに変化が見られます。教育システムも変化し、女子短期大学の4年制大学化や共学化が進みました。
社会構造としては、男女関係だけではなく、会社と労働者の関係も大きく変わりつつあります。高度経済成長時代には、労働者は自分の会社に所属するという意識が強く、会社も労働者を家族のように扱うところもありました。終身雇用を前提とし、会社がさまざまな福利厚生サービスを社員に提供し、会社での飲み会など懇親イベントが多く行われていました。
他方、1990年代以降、会社での働き方は大きく変わることになります。不況の影響もあり、終身雇用という考え方は大きく崩れます。雇用関係も、正社員以外に非正規雇用や派遣社員など、さまざまな形態のものが混じる形になります。労働者はあくまで会社は労働する場であるととらえ、会社の中での懇親イベントも少なくなります。
もう一点、社会構造の変化として挙げられるものに、インターネットの普及による情報社会の進展があります。1990年代後半よりマイクロソフトのWindowsが発売されることでインターネットが社会に普及し、さらに2000年代後半にアップルのiPhoneが発売されることでスマートフォンが普及しました。インターネットやスマホの普及により、個人が自由にさまざまな情報にアクセスでき、さらには自由な情報発信ができるようになりました。こうした情報社会の進展は、価値観の多様化を一層進めることにつながっているといえます。
今の親世代40~50代は、こうした男女雇用機会均等法「以前」の経済成長社会を成長期として過ごし、自ら経験したり、または少なくともそうした社会をまさに生き抜いてきた親に育てられたという世代です。
対して今の20代は、完全に社会構造が大きく変化した「後」に生まれ育っています。育ててきた親世代である40-50代も以前の社会構造から新しい社会構造の変化を体験しているので、以前の社会構造の影響だけでなく、新しい社会構造の影響も受けて育ってきた世代といえます。
つまり、子世代が現在の価値観の中で生きているのに対し、親世代はかつての価値観と現在の価値観の両方を経験しており、そうしたことが両者の世代の価値観にわずかな違いを生み出しているといえます。育った時代が異なると価値観に違いが生まれることはありますが、それぞれの時代を理解したうえでお互いの価値観を理解することが大切です。
お話いただいた先生はこちら
仁愛大学人間学部心理学科教授
森 俊之氏
福井県出身。高校までは県内で育つ。
筑波大学大学院博士課程心理学研究科修了。博士(心理学)。
臨床心理士、公認心理師のカウンセラー資格をもち、
相談活動にも従事。4児の父親。